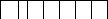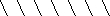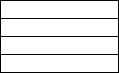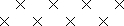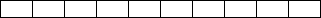○奥出雲町保安林及び保安施設地区に関する事務処理要領
平成21年4月1日
告示第82号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 指定(第2条―第7条)
第3章 解除(第8条―第14条)
第4章 指定施業要件の変更(第15条・第16条)
第5章 異議意見書(第17条)
第6章 保安林における制限(第18条―第23条)
第7章 違反行為(第24条―第31条)
第8章 標識の設置(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 保安林及び保安施設地区の指定、指定の解除その他の保安林及び保安施設地区に関する事務の処理については、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)、森林法施行細則(平成7年3月28日島根県規則第10号。以下「細則」という。)、奥出雲町保安林及び保安施設地区に関する事務取扱要綱(平成21年奥出雲町告示第81号。以下「要綱」という。)その他の法令の定めによるほか、この告示に定めるところによる。
第2章 指定
(指定調査)
第2条 町長は、指定申請書を受理したときは、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、要綱第6条第1項第1号から第4号までの書類を下記により作成するものとする。
(1) 保安林指定調書
ア 保安林指定調書(様式第1号)を作成する。
イ 保安林の指定目的(要綱別表第1)を踏まえ、周辺保安林の指定状況、保安林と受益対象との位置的関係を勘案し指定施業要件を決定する。
ウ 面積の求積は、経緯距法、三斜法、プラニメーター法、点格子板法等により行うものとする。ただし、プラニメーター法により求積を行う場合には、3回以上の平均値を採用するものとする。
(2) 保安林指定位置図
ア 保安林指定位置図は、国土地理院発行の縮尺5万分の1の地形図又は国土地理院の承認を得て市町村が複製した縮尺5万分の1の地形図(通称管内図)により作成するものとする。
イ 作成にあたっては、次の表に掲げる方法により関係事項を図示し、名称等を記載するものとする。
(略号可)
事項 | 図示の方法 | |
要指定区域 | 区域を赤色で塗る | |
受益の対象の存在する区域 | 区域を黄色で塗る | |
既設保安林 | 水源かん養保安林 | 区域を淡緑色で塗る |
土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林 | 区域を淡茶色で塗る | |
その他の保安林 | 区域を淡紫色で塗る | |
既設保安施設地区 | 区域を橙色で塗る | |
(既設保安林については、必ず保安林種を明示するものとする。)
ウ 余白には、森林の所在場所、縮尺、方位、凡例等を記載するものとする。
(3) 保安林指定調査地図
ア 保安林指定調査地図は、森林基本図又は国土基本図を用いて作成するものとする。ただし、地番ごとの指定面積が小さく記載した記号等識別が困難な場合は指定区域の形状等を勘案し、適宜の縮尺で拡大図を作成するものとする。
イ 作成にあたっては、次の表に掲げる方法により図示するとともに、要指定地及び隣接地の地番及び地目(略号可)を明示するものとする。
事項 | 記号 | 備考 |
町村界 |
|
|
字界 |
|
|
地番界 |
|
|
要指定区域 |
| 赤色のハッチングで囲む |
(内側) | ||
禁伐とする区域 |
| 一点破線を黄色で上塗り |
択伐とする区域 |
| 二点破線を黄色で上塗り |
1箇所当たりの皆伐面積の限度を定める区域 |
|
|
伐採種に係る特例のみを定める区域 |
|
|
伐期齢に係る特例のみを定める区域 |
| |
伐採種及び伐期齢に係る特例を定める区域 |
| |
間伐を定める区域 (禁伐、択伐の部分のみに限る) |
|
|
保安林に指定後最初に択伐を行う森林についての択伐率又は植栽本数若しくは樹種を同一とする区域の区画線 |
|
|
植栽の方法・期間及び樹種を定める区域 |
|
|
治山事業に係る施設 |
| 通常、治山事業で用いられている工種の記号を使用し、計画中の施設については施行年度を裸書し、既設の施設については施行年度を括弧書する。 |
ウ 指定区域の周辺に既設の保安林がある場合には、前述の保安林指定位置図の既設保安林の表示方法により図示するものとする。
エ 要指定地が2以上の団地にわたる場合及び保安林指定調査地図が2葉以上にわたる場合には、その関連を明示するものとする。
オ 余白には、森林の所在場所、縮尺、方位、凡例等を記載するものとする。
カ 要指定地が地番の一部である場合には、当該地番の要指定地の部分とそれ以外の部分をメガネ(○―○)で結ぶものとする。
(4) その他必要な書類
ア 指定に際しては、要指定地番に係る不動産登記簿により、森林所有者、地目、面積などを十分調査し、地目が山林及び原野以外の地目の場合は、関係農業委員会の証明書や市町村長の意見書等により法第2条に定義された森林であることを十分確認するものとする。
イ 不動産登記簿上の権利者と現実の権利者が異なる場合(分収契約、売買契約、相続等による権利の移転等)には、分収造林契約書、土地売買契約書、戸籍謄本、住民票等により、権利の有無について確認するものとする。
2 保安林整備計画等に基づく指定調査を行うときも前号の書類を作成し報告するものとする。
3 保安林の指定目的の変更を行う必要があると認められるときには、保安林指定及び解除(保安林種変更)調書(様式第2号)を作成するものとする。ただし、調書に保安林指定・解除位置図、保安林指定調査地図、保安林解除調査地図を作成し添付するものとする。
(指定の告示)
第3条 告示内容の構成は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 複数の告示を同一の告示で取り扱うときには、枝番号を付して区分するものとする。
(2) 保安林の指定目的の変更(林種変更)は次のとおりとする。
ア 林種変更については、解除と指定を同一の告示で取り扱うものとする。
イ 林種変更に係る保安林の指定及び解除が町長権限であるものと知事権限、農林水産大臣権限であるものにまたがる場合には、原則として、指定をした後に解除を行うものとする。
(保安林の所在場所の表示方法)
第4条 保安林の所在場所の表示方法は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 総括的な表示方法
ア 市郡名、町村名、大字名、字名及び地番は重複して表示しない。
イ 同一の字で地番が2以上あるときは、若い地番から表示する。
ウ 地番が3筆以上連続する場合には、「○○から○○まで」と一括して表示する。
エ 2筆以上の全部指定地番を表示する場合には、地番と地番の間に読点を表示する。
オ 1筆の土地の一部を指定する場合の表示方法
(ア) 一部指定地番が1筆である場合には、地番の次に「(次の図に示す部分に限る。)」と表示する。
(イ) 2筆以上の一部指定地番を表示する場合には、地番と地番の間に「・」を表示する。
(ウ) 一部指定地番が2筆以上ある場合には、その最終地番の次に「(以上○筆について次の図に示す部分に限る。)」と表示する。
(エ) 一部指定地番が3筆以上連続する場合には、「○○から○○まで(以上○筆について次の図に示す部分に限る。)」と表示する。
(オ) 第1号イの規定にかかわらず一部指定地番と全部指定地番がある場合には、字ごとにそれぞれ区分し、「4・9(以上2筆について次の図に示す部分に限る。)、2、7」のように表示する。
(カ) 所在場所の名称が市町村名、大字名、又は字名で終わり、地番が付されていない場合には、指定の区域が市町村、大字、字の一部であると全部であるとにかかわらず「(次の図に示す部分に限る。)」と表示する。
(2) その他作成要領
ア 字名が数字の場合には、地番との間を一字あけて表示する。
イ 指定区域において同一の字名中同一地番が存在する場合には、1地番のみを表示し、その指定の地番が1筆の土地の一部であると全部であるとにかかわらず、その地番の次に「(次の図に示す部分に限る。)」と表示する。
ウ 指定施業要件のうち、立木の伐採の方法に係る所在場所の表示には、市郡名、町村名、大字名を表示する必要はなく、字名と地番のみを表示する。ただし、字名の表示がなく、大字名で終わる場合には、大字名から表示する。
エ 指定施業要件のうち、立木の伐採の方法については、1地番(1筆の土地の全部であると一部であるとにかかわらず保安林に指定する場合)に2以上の伐採方法を定める場合には、「(次の図に示す部分に限る。)」と表示し、当該地番が2筆以上ある場合には「次の図」の前に「以上○筆」と表示する。
(縦覧場所の表示方法)
第5条 縦覧場所の表示方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 告示の末尾には「(「次の図」及び「次のとおり」は省略し、その図面及び関係書類を奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)」と表示する。
(2) 告示中に「次の図」及び「次のとおり」がない場合には縦覧事項は表示しない。
(3) 告示中に「次の図」がない場合には、「(「次の図及び」及び「図面及び」)」を削り、「次のとおり」がない場合には、「(「及び次のとおり」及び「及び関係書類」)」を削る。
(4) 指定対象地が無地番(不動産登記簿上所在地番の表示がされていない土地)であって、対象地の接続地又は対象地を取り囲む土地の所在地番が存在する場合には、その代表所在地番に地先の名称を表示し、最後に「(次の図に示す部分に限る。)」と表示する。
(告示の附属明細書)
第6条 告示の附属明細書については、別紙第1号に示す記載例を参考に作成するものとする。
2 帯状の防風保安林及び防霧保安林において、指定施業要件として伐採種を定めない場合には、令別表第2の2の(1)ハに規定する事項を告示の附属明細書に記載し、指定施業要件として定めるものとする。
(保安林予定森林等の名称、地番の変更)
第7条 町長は、申請者から止むを得ず名称、地番の変更が生じた旨の報告がなされた場合には、保安林指定調書を訂正するものとする。
第3章 解除
2 事業区域内に大面積の保安林が含まれる場合、又は保安林の整備経緯、地況、林況、保全対象等の状況から特に問題があると認められる相談等があったときは、次の事項を留意の上、相談者に対し助言指導を行うものとする。
(1) 公共性が認められること。
ア 当該事業の目的、計画内容から、地域住民等の福祉の増進、地域住民の生活基盤、公共施設等の整備に資すると認められるものであること。
イ 事業主体が、地方公共団体、公共性を有する第三セクター、特殊法人であること。
ウ 地方公共団体と整備保全協定を締結するなど公的担保措置が講じられるものであること。
(2) 土地利用の合理性や整合性があり、地域でのコンセンサスが得られていること。
ア 当該事業の目的計画内容等が、地方公共団体が策定している土地利用計画、地域振興計画、その他指導要綱等と整合性を有するものであること。
イ 保安林の指定の目的、配備の状況、指定施業要件の内容等から相当性があり、用地事情において当該土地以外に適地を求め難い状況にあると認められること。
ウ 事業実施に際して保安機能の確保等に支障が生じないよう適正な代替施設の設置等の措置が講じられるものであること。
エ 当該保安林の指定の解除に利害関係を有する者の反対がないこと。
(3) 事業実施による波及効果が期待されること。
ア 当該事業が実施されることにより、地場産業の振興、雇用の創設等に直接的に寄与すると認められるものであること。
イ 事業収益での地域還元(保安林の整備推進、町民の優遇措置等)が期待されるものであること。
3 町長は、法第41条第3項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事若しくは同法第41条のぼた山崩壊防止工事の施工地に係る解除に該当する場合には、県を経由し農林水産大臣に協議するものとする。
(1) 保安林解除調書
ア 申請内容について検討のうえ保安林解除調書(様式第3号)を作成する。
(2) 保安林解除位置図 要指定区域を要解除区域とし、保安林指定調査位置図に準じて作成するものとする。
(3) 保安林解除調査地図
ア 作成にあたっては、次の表に掲げる方法により図示するとともに、要解除地及び隣接地の地番・地目を明示するものとする。(地目については略号可)
事項 | 記号 | 備考 |
町村界 | 保安林指定調査地図における当該事項の記号に準ずる。 |
|
字界 | ||
地番界 | ||
要解除区域 |
| 区域を赤色で塗る。 |
保安林 |
| 区域を青色で囲む。 |
治山事業に係る施設 | 保安林指定調査地図における当該事項の記号に準ずる。 |
|
イ その他作成方法等については、保安林指定調査地図の作成方法等に準ずるものとする。
(4) その他必要な書類
ア 法第26条の2第4項の規定に基づく保安林の指定の解除の協議に係る農林水産大臣の同意が必要となる場合には、下記協議書類を作成するものとする。
(ア) 保安林解除調書
(イ) 事業計画の概要
(ウ) 事業計画の内容審査結果
(エ) 位置図
(オ) 保安林解除調査地図
(カ) 写真
(キ) 事業計画書
(ク) 事業計画図
2 保安林整備計画等に基づく解除調査を行うときも前項の書類を作成し報告するものとする。
(解除の告示)
第10条 告示の表示方法等については、第3条の規定を準用する。
(解除予定保安林の名称、地番の変更)
第11条 解除予定保安林の名称、地番の変更については、第7条の規定を準用する。ただし、申請者が申請から法第33条の解除確定告示までの間に所在場所の名称、又は地番を変更しようとする場合は、行わないよう申請者を指導するものとする。
(解除理由)
第12条 保安林の解除の予定告示及び確定告示の解除の理由は別表第3のとおりとする。
(解除予定保安林における法第34条第2項の許可の取扱い)
第13条 解除予定保安林における(法第30条又は第30条の2第1項の告示の日から40日を経過した後(法第32条第1項の意見書の提出があったときは、これについて同条第2項の意見の聴取を行い、法第30条の2第1項に基づき告示した内容を変更しない場合に限る。))法第34条第2項の許可(以下「作業許可」という。)を行う場合の取扱いは、下記のとおりとする。
(1) 代替施設の設置等に係る事業計画の内容と適合していること。
(2) 代替施設の設置等に係る工事の工程を変更する必要が認められるときは、それぞれの作業許可申請書に変更工程表及び変更理由書を添付させること。
2 解除予定保安林における作業許可において、代替施設の設置等について変更を要することとなった場合には、次のように取り扱うものとする。
(1) 代替施設の位置、工種、規模及び数量等の変更は、当初計画(解除予定保安林の代替施設計画)と比較し、変更内容が軽微であり代替機能が下回らない場合に限り認めるものとする。
(2) 代替施設の設置等に係る変更であって、当該内容を著しく変更し、又は解除予定保安林の変更(法第29条の予定通知の変更)を伴うものは認めないものとする。
(代替施設等の確認)
第14条 町長は、解除予定保安林の作業許可に係る行為が終了した旨の報告がなされたときは、代替施設の設置等が講じられたか確認を行うものとする。
2 代替施設の設置等の確認時期等の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 原則として分割解除(分割確認)は行わない。
(2) 普通林の林地開発行為許可と一体の場合は、これらと完了確認時期を合致させる。
(3) 先行代替施設、本体施設に係る代替施設の順に確認する。
3 代替施設の設置等の確認内容は、次のとおりとする。
(1) 確認する範囲
代替施設等の確認の範囲は、原則として規則第15条第2項第2号の代替施設計画書に記載された事項とする。
(2) 確認に至る手順
ア 確認に当たっては、事前に仕様書、工事完成図、写真等を提出させ、これに基づき確認を行うこと。
イ 代替施設等の設置等に係る事業計画の内容に変更がないか事前に確認し、変更があった場合は、事前に変更に必要な措置を行った上で最終確認を行うこと。
(3) 確認方法
ア 量的な確認
(ア) 代替機能を満足し得るものであれば、局部的な数量の増減は許容し得る。
(イ) 筋工、柵工など数量の多い工種は抽出確認することができる。
(ウ) 確認時点で明視できない部分は写真(寸法表示)等で判断できる。
イ 質的な確認
(ア) 代替機能を保持できる強度であること。
(イ) 仕様書等で規定した規格、工法であること。
(ウ) 確認時点で明視できない部分は写真等で判定できること。
第4章 指定施業要件の変更
(指定施業要件の変更調査)
第15条 町長は、指定施業要件の変更申請書を受理したときは、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、要綱第19条の書類を下記により作成するものとする。
(1) 保安林指定施業要件変更調書
ア 保安林指定施業要件変更調書(様式第4号)を作成する。
イ 保安林指定施業要件変更調書は、保安林指定調査調書に準じて作成するものとする。
(2) 保安林指定施業要件変更位置図
指定施業要件変更位置図については、要指定区域を要指定施業要件変更区域とし保安林指定調査位置図に準じて作成するものとする。
(3) 保安林指定施業要件変更調査地図
ア 作成は、変更後の指定施業要件に関し、次の表に掲げる方法により図示するとともに、要変更地及び隣接地の地番・地目を明示するものとする。(地目については略号可)
事項 | 記号 |
町村界 | 保安林指定調査地図における当該事項の記号に準ずる。 |
字界 | |
要変更地の区画線 |
|
要変更地及びそれに隣接する土地に係る地番地域の境界線 |
|
要変更地を含む1団地の保安林の区域の境界線 |
|
禁伐とする区域 | 保安林指定調査地図における当該事項の記号に準ずる。 |
択伐とする区域 | |
1箇所当たりの皆伐面積の限度を定める区域 | |
伐採種に係る特例のみを定める区域 | |
伐期齢に係る特例のみを定める区域 | |
伐採種及び伐期齢に係る特例を定める区域 | |
間伐を定める区域 | |
保安林に指定後最初に択伐を行う森林についての択伐率又は植栽本数若しくは樹種を同一とする区域の区画線 | |
植栽の方法・期間及び樹種を定める区域 | |
治山事業に係る施設 |
イ その他作成方法等については、保安林指定調査地図の作成方法等に準ずるものとする。
2 保安林整備計画等に基づく指定施業要件変更調査を行うときも前項の書類を作成するものとする。ただし、保安林整備計画の変更(平成14年3月27日変更)に基づく指定施業要件の変更については、下記により書類を作成するものとする。
(1) 指定施業要件変更調書(様式第5号)
(2) 指定施業要件変更調査地図(第15条第1項第3号の地図をいう。同一の告示(保安林の指定(昭和37年7月1日以前に指定された保安林にあっては、その指定施業要件の指定)に係る告示が同じであるものをいう。)に係る保安林のうち、同一地番内のものの一部につき他の部分と異なる内容の指定施業要件の変更を行う場合又は重要流域の民有林、重要流域以外の流域の民有林、林野庁所管の国有林若しくは林野庁所管以外の国有林の区分ごとにその一部につき指定施業要件を変更する場合に限る。)
(指定施業要件変更の告示)
第16条 告示の表示方法等については、第3条の規定を準用する。
第5章 異議意見書
(異議意見書の受理)
第17条 法第32条第1項(法第33条の3において準用する場合を含む。)の意見書の提出がなされた場合には、町長は受理するものとする。
第6章 保安林における制限
(立木伐採許可)
第18条 町長は、立木伐採許可申請書が提出された場合、申請者が当該立木伐採について正当な権原を有していること又は正当な権原を有している者から委任等を受けていることを十分確認するものとする。
2 町長は、立木伐採許可申請書を受理したときは、別添「保安林における立木伐採等許可申請、届出に対する適否判定等の調査要領」(以下「適否判定等調査要領」という。)により実地調査を行うとともに適否の判定を行うものとする。
3 許可に付する条件は、要綱第26条に定めるところによるほか、次の事項について付するものとする。
(1) 保安林立木伐採許可標識を現地に表示すること。
(2) その他必要な事項
4 皆伐による伐採であって、伐採面積の調整を図る必要が生じた場合には、農林振興センターと協議を行うものとする。
5 町長は、審査の結果、不許可の決定をしたときは不許可の理由を明記した不許可決定通知(様式第6号)を申請者に送付するものとする。
6 町長は法第34条第8項の届出があった場合には、これを受理し適否判定等調査要領により伐採の照査を行う。ただし、提出された届出書の書式、記載事項等に不備がある場合には許可申請の受理に準じて処理するものとする。
7 伐採期間の満了後30日を経過しても法第34条第8項の伐採の届出がない場合には、伐採の有無を確認する。この場合において、伐採を終了しているときは届出をするよう指導するものとする。
9 指定施業要件として、植栽の方法・期間及び樹種が定められている保安林において立木の伐採が行われた場合は、当該植栽の期間の満了後速やかに、指定施業要件の定めるところに従って植栽が行われたかどうかを適否判定等調査要領により調査する。
(作業許可)
第19条 作業許可の許可基準は、要綱別表第6に掲げる基準のほか下記に定めるところによるものとする。
(1) 作業許可申請に係る行為が、周辺地域に土砂の流出等の被害を及ぼすおそれがある場合、立木の生育を阻害し又は土壌の性質を改変する等保安林の保安機能の低下をもたらすと認められる場合には、許可しないものとする。
(2) 指定施業要件で禁伐等と定められている保安林内においては、許可しないものとする。
(3) 林道については、車道幅員が4メートル以下であって、森林の施業・管理に供するため周囲の森林と一体として管理することが適当と認められる場合に作業許可の対象とするものとする。この場合において、農道、市町村道その他の道路が森林内に設置され、その規格・構造が林道と同等のものであって、森林の施業・管理に資すると認められるものに限り林道と同様に取扱うものとする。
(4) 森林の保安機能の維持・強化に資する施設とは、その設置目的・構造からみて保安機能を持つことが明らかであって、周囲の森林と一体となって管理することが保安林の指定の目的の達成に寄与すると認められる場合に作業許可の対象とする。
(5) 保安林の転用に伴い設置する代替施設で転用に係る区域内に設置する施設については、本体施設と一体となって管理すべきものであり、作業許可の対象としないものとし、転用区域外に設置する施設であっても、洪水調整池等の森林を改変する程度が大きいものについても作業許可の対象としない。
(6) 物件の堆積等に係る作業許可において、土砂捨て、しいたけ原木等の堆積、仮設工作物の設置等の一時的な変更行為に係る作業許可は、土壌の性質、林木の生育に及ぼす影響が微少であると認められるものに限って行うものとする。
(7) 作業許可申請の内容が許可基準に適合するものであっても、当該保安林の指定の目的、指定施業要件、現況からみて保安機能の維持に支障を及ぼすおそれがある次のような場合には画一的に許可を行うことは適当でなく、慎重に判断するものとしている。
ア 急傾斜地である等個々の保安林の地形、土壌又は気象条件等により、変更行為が周囲の森林に与える影響が大きくなるおそれがある場合
イ 風致保安林内での景観を損なう施設の設置等その態様が保安林の指定の目的に適合しない場合
ウ 変更行為が立木の伐採を伴う場合において、その態様が当該保安林の指定施業要件に定める伐採の方法、限度に適合しない場合
エ 変更行為により、当該保安林の大部分が森林でなくなる等保安林としての機能を発揮できなくなるおそれがある場合
2 町長は、作業許可申請書を受理したときは、申請者が当該立竹等の伐採、土地の使用について正当な権原を有していること又は正当な権原を有している者から委任等を受けていることを確認のうえ、適否判定等調査要領により実地調査を行うとともに適否の判定を行うものとする。
3 町長は、許可に当たっては、保安林として適正な林地の利用が確保されるよう次の事項に留意すること。
(1) 申請に係る行為が計画書のとおり確実に実施されること。
(2) 申請に係る行為により当該保安林の保全対象が害されることがないこと。
4 許可に付する条件は、要綱第32条に定めるところによるほか、次の事項について付するものとする。
(1) 事業の着手時及び完了時には、遅滞なくその旨を届け出ること。
(2) 許可年月日、許可内容、期間、氏名等が明記された許可標識等を現地に表示すること。
(3) 施設等を設置した場合には適切に保守、管理を行い、有責事由により災害が発生した場合は災害復旧の責務を負うこと。
(4) 町の職員により現地指示(補正のための施工に係るものを含む。)等が行われた場合は、これを遵守すること。
(5) 監督処分、許可の取消し等に該当すること。
(6) その他事業者に徹底すべきこと。
6 町長は、許可を行った場合には必要に応じ現地の巡回、調査等を行い、許可に係る行為の実施状況等を把握するものとする。
7 町長は、事業が完了した旨の届出がなされたときは、施行の結果を適否判定等調査要領により照査するものとする。
8 町長は、調査等の結果、行為の内容が申請の内容と異なる場合又は許可に付した条件に従っていない場合には、当該許可を受けた者に対し、当該行為を是正するよう指導を行い、是正されない場合には、復旧命令等適切な措置を講ずるものとする。
9 町長は、管理台帳(様式第11号)を調製し、許可に至る経緯、許可に係る土地の所在場所及び面積、行為の概要、行為の期間、現地指導等の特記事項、施設等の維持・管理の状況その他必要な項目について整理するものとする。
(立木伐採の届出及び土地の形質の変更の届出)
第20条 町長は、立木伐採の届出及び土地の形質の変更の届出がなされたときは、当該立木等の伐採、土地の使用について正当な権原を有していること又は正当な権原を有している者から委任等を受けていることを確認のうえ、適否判定等調査要領により実地調査を行うとともに適否の判定を行うものとする。
2 適否判定の結果適正と認めるときは、その旨を書面で通知(様式第12号)するものとする。
(択伐及び間伐の届出)
第21条 町長は、択伐届出書又は間伐届出書を受理したときは、申請者が当該立竹等の伐採、土地の使用について正当な権原を有していること又は正当な権原を有している者から委任等を受けていることを確認のうえ、適否判定等調査要領により実地調査を行うとともに適否の判定を行うものとする。
2 適否判定の結果適正と認めるときは、その旨を書面で通知(様式第12号)するものとする。
(緊急伐採及び緊急作業行為)
第22条 法第34条第1項第6号及び第2項第4号に規定する緊急伐採及び緊急作業行為の協議がなされた場合には、急迫の危害の防止又は軽減するため止むを得ないと認められる場合に限り認めるものとする。
(伐採整理簿の調製及び事務実施状況の報告)
第23条 町長は、保安林における立木の伐採の許可又は択伐又は間伐の届出の受理等に当たり、その状況を明らかにするため、伐採年度ごとに、立木に係る伐採整理簿を調製し、併せて事務の実施状況を取りまとめ、知事に次に定める期日までに報告するものとする。
(1) 伐採整理簿
ア 皆伐による立木の伐採許可に関する報告
皆伐による立木の伐採許可(同意)を行った場合には、2月1日、6月1日、9月1日、12月1日公表に係る伐採許可についてそれぞれ5月15日、8月15日、11月15日、1月15日までに伐採整理簿1の写しにより報告するものとする。
イ 択伐による立木の伐採許可等に関する報告
当該年度における択伐による立木の伐採については、伐採整理簿2の写しにより翌年度の5月15日までに報告するものとする。
ウ 伐採届出に関する報告
当該年度における法第34条第9項(緊急伐採)及び規則第22条の8第1項各号の届出に係る立木の伐採については、伐採整理簿3の写しにより翌年度の5月15日までに報告するものとする。
エ 間伐届出に関する報告
当該年度における間伐のための伐採については、伐採整理簿4の写しにより翌年度の5月15日までに報告するものとする。
(2) 事務実施状況
ア 立木伐採等許可事務の実施状況報告
当該年度における立木伐採等許可事務の実施状況は、第2表「保安林・保安施設地区内立木伐採等許可事務実施表」の「(1)立木伐採の許可」により、法第34条第1項の規定に基づく立木の伐採の許可について、また、「(2)立竹伐採等の許可」及び「(2)―2開墾その他の土地の形質の変更の内訳」により、法第34条第2項の規定に基づく立竹の伐採等の許可について取りまとめ、翌年度の5月15日までに報告するものとする。
イ 立木伐採等協議事務の実施状況報告
当該年度における立木伐採等協議事務の実施状況は、第3表「保安林・保安施設地区内立木伐採等協議事務実施表」の「(1)立木伐採」により、規則第22条の8第1項第10号の規定による立木の伐採の協議について、また、「(2)立竹伐採等」及び「(2)―2開墾その他の土地の形質の変更の内訳」により、規則第22条の11第1項第5号の規定による立竹の伐採等の協議について取りまとめ、翌年度の5月15日までに報告するものとする。
ウ 緊急立木伐採等届出事務の実施状況報告
当該年度における緊急立木伐採等届出事務の実施状況は、保安林・保安施設地区内緊急立木伐採等届出事務実施表(様式第13号)により、法第34条第9項の規定による届出について取りまとめ、翌年度の5月15日までに報告するものとする。
エ 立木伐採届出事務の実施状況報告
当該年度における立木伐採届出事務の実施状況は、保安林・保安施設地区内立木伐採届出事務実施表(様式第14号)の「(1)択伐」により、法第34条の2第1項の規定による択伐の届出について、また、「(2)間伐」により、法第34条の3第1項の規定による間伐の届出について取りまとめ、翌年度の5月15日までに報告するものとする。
オ 植栽の状況報告
当該年度における植栽の状況は、植栽(様式第15号)により、主伐が実施された森林について、伐採年度ごとに指定施業要件で植栽義務が課せられた森林における植栽について取りまとめ、翌年度の5月15日までに報告するものとする。
カ 違反行為及び是正措置の実施状況報告
当該年度における違反行為及び是正措置の実施状況は、保安林・保安施設地区違反行為及び是正措置実施表(様式第16号)により、調査年度内に発生した違反行為事案、調査年度内に違反是正措置を実施した事案及び調査年度以前に発生した違反行為事案であって調査年度末までに是正行為(造林、復旧又は植栽をいう。)が実施されていない事案のすべてについて取りまとめ、翌年度の5月15日までに報告するものとする。
キ その他
当該年度におけるその他の保安林管理に係る事務実施について、その状況を明らかにする必要がある場合は、関係資料を整理し、知事に報告するものとする。
第7章 違反行為
(違反行為の実態把握及び行為の中止)
第24条 町長は、違反行為の疑いがある行為を発見したとき又はその旨の連絡を受けたときは、速やかに現地調査を行い、違反行為が確認されたときには、その場で口頭で行為の中止及び必要に応じて防災対策を指示し、保安林内違反行為調書(様式第17号)を作成する。
(復旧の指示)
第25条 町長は、違反行為者に対しては、違反の内容を十分了知させ、行為の中止並びに始末書及び復旧計画書の提出を指示するものとする。
(復旧計画の承認)
第26条 町長は、違反行為者から復旧計画書が提出された場合には、内容を審査し保安林の機能の維持、回復が図られると判断したときは、違反行為者に復旧計画実施通知(様式第18号)を行うものとする。
(1) 命ずる相手方命令に係る土地の所在場所を特定すること。
(2) 命令書を郵送する場合は、内容証明付き郵便で行うこと。
2 町長は、復旧工事の施工中において、必要に応じ調査し、復旧等の措置が適正に履行されるよう指示、指導するものとする。
(完了確認)
第29条 町長は、復旧(命令)工事完了届が提出された場合には、履行状況を確認し、復旧(命令)工事確認調書(様式第25号)を作成するものとする。
(告発)
第30条 町長は、違反行為者が第27条の監督処分に従わないときは、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、違反行為者を告発することができる。
(国有保安林内での違反行為の対応)
第31条 林野庁所管の国有保安林内における違反行為に係る監督処分も第27条と同様の措置を講ずるものとする。
第8章 標識の設置
(標識の設置等)
第32条 標識の種類の選択に当たっては、設置の効果及び維持管理の効率性を考慮し、次の各号に定める標識を設置する。
(1) 第1種標識 主として多雪地及び海岸地域の保安林に設置
(3) 第3種標識 保健保安林又は都市近郊地等にあって管理上特に留意すべき保安林に設置
2 町長は、計画的な標識の維持管理のため、標識の設置時期、設置場所、その他必要な事項を記載した保安林標識整理簿(様式第28号)を調整・保管すること。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
保安林転用解除申請書の添付書類及び編成順序
編成順序 | 必要添付書類 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | |
迅速化通達 | 運用改善通達 | 簡素化通達 | ||||
1ha以下で、公益上の理由及び形質変更が軽微な事業 | 専ら道路の新設又は改良(高速自動車国道を除く) | 国・地方公共団体の行う事業又は施行規則第3条で定める事業 | その他すべての解除 | |||
1 | 進達書又は申請書 | ※進達書:事業者が県の機関以外の場合 申請書:事業者が県の機関で知事名で申請する場合 | ||||
2 | 知事意見書 | ※保安林解除申請書を知事名以外で申請する場合 | ||||
3 | 保安林解除調書一覧表 | ※保安林解除調書が2以上になる場合 | ||||
4 | 保安林解除調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 保安林解除調書附属明細書 | ※保安林が2筆以上のとき、又は森林所有者若しくは森林に関する登記済権利者が2人以上のとき | ||||
6 | 共有林所有者名簿 | ※森林が共有林であるとき | ||||
7 | 事業計画の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 事業計画の内容審査結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 島根県森林審議会答申書の写し | ※保安林の解除に係る事業等が国又は地方公共団体以外で行われるもので、保安林解除面積が1ha以上のもの | ||||
10 | 国有林を管理する国の機関の長の意見 | ※申請に係る森林が国有林である場合(国有林野又は官行造林地にあっては、近畿中国森林管理局長の意見) ※意見の聴取は県庁森林整備課で行う | ||||
① | 保安林解除申請書又は依頼書 | ※申請書:事業者が県の機関以外の場合 依頼書:事業者が県の機関である場合(所轄の農林振興センター所長あて)知事の権限の場合は申請書 | ||||
② | 保安林解除位置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
③ | 保安林解除調査地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
④ | 保安林解除図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑤ | 現況写真 | 全景のみ | ※保安林界等を書き入れた全景(航空写真)及び森林の状況写真 | |||
⑥ | 事業計画図(平面図) | 事業施設及び代替施設の配置は、同一の図面に表示で可 | ||||
⑦ | 事業計画書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑧ | 1 | 工事設計書 | × | × | × | × |
2 | 工事仕様書 | × | × | × | × | |
3 | 排水施設計画流量計算書 |
| × |
| ||
4 | 流出土砂貯留施設計算書 | × | ||||
5 | 洪水調節施設等計算書 | 各計算書のとりまとめ表(箇所毎に因子、計算値、安全率及び公式を記載)についてのみの記載で可 | ||||
⑨ | 予算又は残高証明書の写し等資金の調達方法を証する書類 | ○ | × | × | ○ | |
⑩ | 代替施設計画書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑪ | 代替施設安定計算書 |
| × |
| ||
各計算書のとりまとめ表(箇所毎に因子、計算値、安全率等及び公式を記載)についてのみの記載で可 | ||||||
⑫ | 他法令による許認可書等の写し、又は申請の状況を記載した書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑬ | 直接利害関係者の同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑭ | 市町村長の同意書 | ○ ※あて名は知事名とする(事業者あてとはしない) | × (市町村が事業主体の解除申請又は市町村長が申請者であるもののみ) | ○ | ||
⑮ | 1 | 法人登記簿、規約等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 定款、営業報告書 | ○ | ○ | × | ○ | |
⑯ |
| 直接利害関係者の証書 |
| |||
| 1 | 登記事項証明書 | ○ | △ | △ | ○ |
2 | 土地使用承諾書、売買契約書の写し等(登記名義人と申請者が異なる場合) | ○ | △ | △ | ○ | |
3 | 土捨場土地使用承諾書 | ○ | × | ○ | ○ | |
⑰ |
| 土量計算書等の書類 |
| |||
| 1 | 土量配分計画平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 土量計算書 | 切土、盛土及び残土について総量並びにその処理方法のみの記載で可 | ||||
3 | 土捨場土量(容量)計算書 |
| × |
| ||
土捨場容量計算とりまとめ表についてのみの記載で可 | ||||||
⑱ | 1 | 面積計算図(丈量図) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 面積計算書 | 面積計算とりまとめ表についてのみの記載で可 | ||||
⑲ |
| 事業計画に関する実施設計図 |
| |||
| 1 | 縦横断面図 | 標準的切土及び盛土の断面のみを同一の図面に表示(法面の高さ、土質別の勾配等を表示)した標準断面図(1葉)で可※土工定規図 | ○ | ○ | |
2 | 構造図 | ○ | × | ○ | ○ | |
3 | 土工定規図 | × | × | ○ | ○ | |
4 | 土捨場平面図 | ○ | × | ○ | ○ | |
5 | 土捨場縦・横断面図 | ○ | × | ○ | ○ | |
6 | 集水区域図 | ○ | × | ○ | ○ | |
7 | 排水計画平面図 | ○ | × | ○ | ○ | |
8 | 流末処理計画平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 流出土砂貯留施設平面図 | ○ | × | ○ | ○ | |
10 | 洪水調節施設等平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑳ |
| 代替施設計画に関する実施設計図 |
| |||
| 1 | 代替施設配置図 | ※⑤ 事業計画図に記入したときは不要 | |||
2 | 縦・横断面図 | ※⑱―1 縦横断面図に記入したときは不要 | ||||
3 | 構造図 | ○ | × | ○ | ○ | |
((21)) | その他参考となる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注1
○:添付を要するもの。
△:添付を要するものであるが、国への申請書には省略してよいもの。
記述:簡略化してよい内容。
×:添付を省略してよいもの。
※:書類等作成にあたっての留意事項。
2 ここに記載の添付書類は標準的なものであるので、解除の案件によっては書類等の追加を必要とする場合もある。
3 図面がA4判又はA3判折り込みにできる場合には、関連事項の次に綴じ込んでもよい。
別表第2(第8条関係)
事業計画書及び代替施設計画書に添付すべき図面
番号 | 図面の種類 | 明示すべき事項 | 注意事項 |
| 現況図 | ①地形(1~2mの等高線) ②行政区界 ③事業区域界(黒太線) ④保安林界(藍) ⑤解除申請区域 (赤くうすく着色) ⑥他法令規制区域及びその名称 ⑦土地利用現況 (森林、農地、道路、宅地等) ⑧人家・公共施設等 ⑨治山施設の位置、種類及び施行年度 ⑩保安林の傾斜区分 (25°未満、25°以上) ⑪添付写真の撮影位置及び方向 | スキー場、農用地等のような大規模な転用の場合に作成することとし、一般には省略してよい。 1 縮尺1/500~1/2,000 |
⑥ | 事業計画図 | ①地形(1~2m等高線入り) ②地番界(地番、地目記入) ③事業区域界(黒太線) ④保安林界(藍) ⑤解除申請区域 (赤くうすく着色) ⑥土地利用計画 (施設の配置及び名称) ⑦法面の位置、形状小段 ⑧切土、盛土の区分 ⑨えん堤、擁壁、排水施設の位置、記号又は番号、種類及び規模等の代替施設の配置 ⑩縦横断測点又は測線 | 1 縮尺1/500~1/2,000 2 工種別(道路、排水施設等)に色別すること。 3 残土処理箇所についても同様に作成すること。 4 事業計画図と代替施設配置図を合併し作成してもよい。この場合には、標題を「事業計画図兼代替施設配置図」とすること。 |
⑳―1 | 代替施設配置図 | ||
⑰―1 | 土量配分計画平面図 | ①事業区域界(黒太線) ②造成区域界 ③保安林界(藍) ④切土区域 (黄色でうすく着色) ⑤盛土区域 (桃色でうすく着色) ⑥切土並びに盛土部分の位置形状及び土量 ⑦土砂の移動方向及び移動土量 | 1 縮1尺1/500~1/1,000 |
⑱―1 | 面積計算図 (丈量図) | ①保安林界(藍) ②解除申請区域 (赤くうすく着色) | 1 縮尺1/500~1/1,000 2 解除申請区域は三斜法又は座標法による。 |
⑲―1 | 縦断図 | ①測点 ②区間距離 ③追加距離 ④地盤高 ⑤計画高 ⑥切土高 ⑦盛土高 ⑧匂配 ⑨保安林解除の申請区間(赤) | 1 縮尺 〔水平〕1/1,000~1/2,000 〔垂直〕1/200~1/400 2 土石等の採掘にあっては年度別掘削断面及び採掘量計算表を表示すること。 |
横断図 | ①測点 ②切土又は盛土高 ③現地盤線 ④計画地盤線及び匂配 ⑤擁壁及び法面保護施設 ⑥保安林解除の申請区間(赤) | 1 縮尺1/100~1/200 2 土石等の採掘にあっては、年度別掘削断面及び採掘量計算表を表示すること。 | |
⑲―2 | 構造図 | ①構造各部の仕上り寸法 ②材料の種類及び寸法 ③基礎工の材料及び寸法 | 1 縮尺1/20~1/200 2 正面図、平面図、側面図、断面図及び配筋図等で図示すること。 |
⑲―3 | 土工定規図 (標準断面図) | ①地質又は土質別の切土匂配及び盛土匂配 ②小段の位置、幅及び間隔 ③擁壁及び法面の保護施設 ④仕上り寸法(道路) ⑤造成地盤の匂配(宅地造成) | 1 縮尺1/100~1/200 |
⑲―4 | 土捨場平面図 | ※ 事業計画図に準ずる。 |
|
⑲―5 | 土捨場縦・横断面図 | ※ 縦・横断面図に準ずる。 |
|
⑲―6 | 集水区域図排水計画平面図 | ※ 縦・横断面図に準ずる。 ①集水区域界(色別) ②集水区域の番号及び面積 | 1 縮尺1/500~1/5,000 2 集水区域及び排水施設の記号又は番号は排水施設計画とりまとめ表と対照できるように表示すること。 |
⑲―7 | 排水計画平面図 | ①集水区域界(色別) ②集水区域の番号及び面積 ③排水施設の位置、記号又は番号、種類、形状、内のり寸法、匂配、延長水の流れの方向及び放流先の名称 ④保安林界(藍) ⑤排水系統模式図を図面の余白に記載 | 1 縮尺1/500~1/2,000 2 集水区域及び排水施設の記号又は番号は排水施設計画とりまとめ表と対照できるように表示すること。 3 必要により「工事中」「工事後」に分けて作成すること。 |
⑲―8 | 流末処理排水計画図 | ①集水区域界(色別) ②集水区域の番号及び面積 ③事業区域 ④下流河川の名称 ⑤流下能力の検討地点及び縦横断面 ⑥現況写真(ポール等で大きさを表示)を添付 | 1 縮尺1/1,000~1/5,000 2 排水施設計画とりまとめ表と対照できるように表示すること。 |
⑲―9 | 流出土砂貯留施設平面図 | ①集水区域界(色別) ②集水区域の番号及び面積 ③土砂流出防止施設(色別)の位置記号又は番号、種類規模及び貯砂量 ④保安林界(赤) | 1 縮尺1/500~1/2,000 2 集水区域及び施設の記号又は番号は土砂流出防止施設計画とりまとめ表と対照できるように表示すること。 3 えん堤等の実測縦横断図及び貯砂量計算書を別に添付すること。 4 必要により「工事中」と「工事後」に分けて作成すること。 |
別表第3(第9条関係)
保安林の解除の理由
1 法第26条第1項及び法第26条の2第1項関係(指定理由の消滅)
分類 | 細分類 | 摘要 |
農地 | 農業用地 | 田畑の開墾、果樹園、茶園、桑園等の造成及び用排水等附帯施設 |
草地 | 採草放牧用地 | 採草地、放牧地の造成及び牧道、畜舎等附帯施設 |
畜舎用地 | 牛馬、豚、鶏等家畜飼養施設 | |
宅地 | 住宅用地 | 宅地(住宅団地を含む)及び道路、駐車場、団地内の遊園地、緑地、公共施設敷地、防災施設等の附帯施設用地 |
建物用地 (住宅用地除く) | 事務所、倉庫、車庫、病院、給油所、店舗等主として営業用建物 | |
保健休養 | ゴルフ場用地 | ゴルフ場コース及びクラブハウス、道路、駐車場、防災施設等附帯施設 |
別荘用地 | 建物敷地及び道路、駐車場、公園、防災施設等の附帯施設 | |
スキー場用地 | ゲレンデ及びリフト、道路、駐車場、売店等の附帯施設 | |
スポーツ施設用地 | 運動場、体育館、ゴルフ練習場、テニスコート、サイクリングロード等のスポーツ施設 | |
観光娯楽施設用地 | 屋内遊戯場、遊園地、動植物園、売店等の観光・娯楽施設 | |
宿泊施設用地 | ホテル、旅館、登山小屋等 | |
工場 | 工場用地 | 工場、倉庫、事務所等の敷地及び緑地、環境施設用地 |
土石採掘 | 土砂採掘用地 | 玉石、砂利、砂、砕石原石、土木建築用石材、工業原料等の土石採掘 |
新エネルギー | 風力発電施設 | 風力発電施設、変電所、道路、防災施設等の附帯施設用地 |
風力以外の発電施設 | 風力以外の新エネルギーによる発電施設、変電所、道路、防災施設等の附帯施設用地 | |
その他 |
| 転用目的に応じ適宜細分類名称とする。 |
備考
1 「解除の理由」は「指定理由の消滅」とする。
2 本表によりがたいものは、その都度決定するものとする。
2 法第26条第2項又は法第26条の2第2項関係
分類 | 細分類(解除理由) | 土地収用法第3条該当号又は適用法 |
道路 | 道路用地 | 1 |
駐車場用地 | 1 | |
河川 | ダム用地 | 2 |
河川管理施設用地 (ダム用地除く) | 2 | |
砂防 | 砂防施設用地 | 3 |
地すべり防止施設用地 | 3の2 | |
急傾斜地崩壊防止施設用地 | 3の3 | |
林道 | 林道用地 | 森林法 |
農道 | 農道用地 | 5 |
土地改良 | 用排水路用地 | 5、6、34の2 |
土地改良事業用地 | 5、6 | |
港湾・漁港 | 港湾施設用地 | 10 |
漁港施設用地 | 10 | |
海岸 | 海岸保全施設用地 | 10の2 |
通信施設 | 無線施設用地 | 14 |
電気通信設備用地 | 15、15の2 | |
放送設備用地 | 16 | |
電気工作物 | 電気工作物施設用地 | 17 |
発電施設用地 | 17の2 | |
送電変電施設用地 | 17の2 | |
鉱業 | 鉱業用地 | 鉱業法 |
その他 | 鉄道用地 | 7、7の2、7の3 |
軌道用地 | 7の2、8 | |
索道用地 | 7 | |
飛行場用地 | 12 | |
航空保安施設用地 | 12 | |
気象観測施設用地 | 13 | |
ガス工作物 | 17の3 | |
水道事業用地 | 18 | |
下水道事業用地 | 18 | |
学校教育用地 | 21 | |
社会教育施設用地 | 22 | |
社会福祉施設用地 | 23 | |
公的医療施設用地 | 24 | |
火葬場用地 | 25 | |
と畜場用地 | 26 | |
廃棄物処理施設用地 | 27 | |
保健衛生施設用地 | 24、27 | |
国立公園事業用地 | 29 | |
国定公園事業用地 | 29 | |
公共住宅用地 | 30 | |
都道府県立公園事業用地 | 32 | |
公園用地 | 32 | |
公共施設用地 | 31、32 |
備考
1 土地収用法第3条該当号の欄は、細分類の事項に該当する土地収用法第3条各号を記載したものである。ただし、当該分類によりがたい場合は、その都度適宜定めることとする。
2 いわゆる「多目的ダム」や発電用のダムは、細分類「ダム用地」に含めること。
3 細分類「土地改良事業用地」とは、圃場整備、農地の新規造成等面的な事業の用に供するものとすること。
4 いわゆる「ため池」は、細分類名「土地改良事業用地」に含めること。
5 林道用地及び鉱業用地の土地収用法第3条該当号欄は、当該事業用地の収用を規定する個別法を記載
様式 略