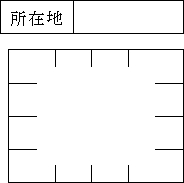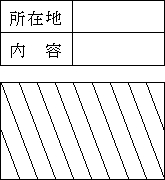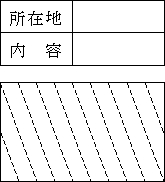○奥出雲町保安林適正管理現況調査要領
平成21年4月1日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、民有保安林について、その現況等を明らかにするとともに、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく適正な管理を行うために必要な情報を得ることを目的とする。
(調査対象保安林)
第2条 調査対象保安林は、平成13年度末現在の民有保安林とし、各保安林における境界の錯綜状況、保安林配備状況及び管理状況等による調査必要度等を勘案し選定する。
(調査項目及び調査内容)
第3条 調査項目及び調査内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保安林境界の実態
境界確認等調査(境界標識の現状確認、要整備優先度把握)
(2) 保安林標識の設置状況
標識確認等調査(設置状況・破損状況確認、要設置(改設定)標識把握)
(3) 保安林機能の実態
保安林機能把握調査(荒廃状況・要樹種改良・要保育等の箇所把握)
(4) 保安林の入り込み等の状況
入り込み状況調査(地元住民・巡視員からの聴取)
自主的管理状況調査(管理主体・内容等の把握)
土地利用状況等調査(転用・不法投棄等の土地利用現況把握)
(5) 地目未更正箇所の実態
地目未更正箇所把握調査(保安林台帳・土地登記簿・地籍簿等照合確認、要整備優先度把握)
(6) 保安林所有者等の実態
権利関係の把握(分筆・合筆の実態や相続関係の実態把握)
不在所有者把握等調査(不在者数、管理状況等把握)
(調査単位)
第4条 調査単位については、保安林をあらかじめ団地に区分する。団地とは、保安林の種類により分けられた一連の保安林の広がりとし、適宜字名等を付して団地名(道路敷等により分断される場合は、これを連続しているものとみなす)とし、また、適宜番号を付するものとする。
(1) 団地が1ヘクタール以下の小面積となる場合は、同じ市町村内の同じ保安林の種類の団地に合わせて1団地とする。
(2) 団地が複数の流域にまたがる場合は、流域ごとに別団地とする。
(3) 団地が複数の市町村にまたがる場合は、市町村ごとに別団地とする。
(4) 団地がきわめて大面積である場合は、地形等により複数の団地に分けることができる。
(団地区分整理表及び調査原図の作成)
第5条 現地調査等実施に当たっては、あらかじめ団地区分整理表(様式第1号)を作成するとともに調査原図を作成するものとする。なお、調査原図は、保安林管理図の写しを使用し、所要事項を記入して作成することとする。
記載事項 | 図示の方法 |
1 流域界及びその名称 | 流域界は黒色の太実線で図示し、名称は黒色で表示するものとする。 |
2 団地界、団地名及び番号 | 団地界は、他の団地との境界については赤色の中実線で図示し、それ以外の部分は次の保安林界をもってこれに替える。団地名及び番号は黒色で図示(大きさは4号活字程度)する。 |
3 保安林界 | 保安林界は、第6条第1号ウの保安林境界の図示の方法により図示する。 |
4 保安林の種類 |
|
(1) 1号保安林 | 保安林界の内縁部を彩色(淡緑色)するとともに適宜の位置に(水)と図示(大きさは4号活字程度とする。以下同じ。)する。 |
(2) 2号保安林 | 保安林界の内縁部を彩色(淡茶色)するとともに適宜の位置に(土流)と図示する。 |
(3) 3号保安林 | 保安林界の内縁部を彩色(淡茶色)するとともに適宜の位置に(土崩)と図示する。 |
(4) 4号~9号保安林 | 保安林界の内縁部を彩色(淡橙色)するとともに適宜の位置に飛砂防備保安林にあっては(飛)、防風保安林にあっては(風)、水害防備保安林にあっては(水害)、潮害防備保安林にあっては(潮)、干害防備保安林にあっては(干)、防雪保安林にあっては(雪)、防霧保安林にあっては(霧)、なだれ防止保安林にあっては(な)、落石防止保安林にあっては(落)、防火保安林にあっては(火)、魚つき保安林にあっては(魚)、航行目標保安林にあっては(航)と図示する。 |
(5) 10号及び11号保安林 | 保安林界の内縁部を彩色(淡青色)するとともに適宜の位置に保健保安林にあっては(保)、風致保安林にあっては(致)と図示する。 |
5 字、地番界、地番 | 現地調査に際し必要な字及び地番については、保安林台帳、同付属図、保安林管理図及び土地登記簿等から調べ、黒色で調査原図に記入すること。 |
6 その他 | その他本調査を行うに当たって参考となる事項については、保安林管理図等適宜記入するものとする。 2種以上の保安林が重複指定されている兼種保安林については、保安林のそれぞれの略号を連記するとともに、それぞれの保安林の内縁周辺部彩色を適宜交互に彩色する。この場合、内縁周辺部彩色が同一の場合は破線状に彩色するものとする。 |
(調査)
第6条 次の各号に掲げる調査における調査内容及び方法については、次のとおりとする。
(1) 保安林境界調査及び保安林標識調査
ア 保安林境界調査は、現地及びその他の資料による保安林境界を調査するものとし、保安林標識調査は、現地及びその他の資料による保安林標識の設置状況、今後設置を要する保安林標識の種類、位置及び本数についての調査するものとする。
イ 調査の結果は、保安林境界、保安林標識調査表(様式第2号)にとりまとめるものとする。
ウ 前条の規定により作成した調査原図に、次により調査結果を記入して調査図を作成するものとする。
記載事項 | 図示の方法 | ||||
保安林境界 | 明りょうな地形、地物界等で特定される保安林界については赤色の実線で、その他の保安林界については赤色の中破線で図示する。 | ||||
保安林標識 |
| (既設) | (計画) |
| |
|
|
|
|
| |
| 青色で縁取り、既設については同色で彩色する。 | ||||
1種標識 | ● | ○ |
| ||
2種標識 | ▲ | △ | |||
3種標識 | ■ | □ | |||
|
|
|
| ||
|
| ||||
(2) 保安林機能調査
ア 森林簿、航空写真、保安林管理図等の資料及び現地調査に基づき、当該保安林の指定の目的を達成するため、荒廃地のあるもの、樹種林相の改良及び保育の適正化を要するもの、施業上留意すべきもの等について調査するものとする。
イ 調査の結果は、保安林機能調査表(様式第3号)にとりまとめるものとする。
ウ 前条の規定により作成した調査原図に、次により調査結果を記入して調査図を作成するものとする。
記載事項 | 図示の方法 | |
保安林機能の現状 |
| 茶色の細実線で囲み、ケバを付すとともに機能区分及び字地番を付記すること。なお、団地全体が対象の場合は、当該団地の周辺余白に「機能区分A」のように茶色で記入し、上記の図示は省略してもよいものとする。 |
(3) 保安林入込調査
当該集落の住民及び森林保全巡視指導員等からの聴取調査により、保安林入込調査表(様式第4号)にとりまとめるものとする。
(4) 保安林の自主的管理実施状況調査
地域住民等による保安林の自主的管理の実施内容等について、保安林自主的管理実施状況調査表(様式第5号)にとりまとめるものとする。
(5) 保安林内の土地利用状況調査
ア 保安林内における他の土地利用(法第34条第2項の許可を受けたものを除く。)等の有無及びその状況等について、現地調査を行うものとする。
イ 調査の結果は、保安林内の土地利用状況調査表(様式第6号)にとりまとめるものとする。
ウ 前条の規定により作成した調査原図に、次により調査結果を記入して調査図を作成するものとする。
記載事項 | 図示の方法 | |
転用 |
| 当該箇所を桃色の細線で囲み、桃色の細斜線を入れるとともに、他の土地利用等の形態、内容、面積及び地番を付記すること。なお、指定前からのものについては※印を付すること。 |
その他 |
| 当該箇所を桃色の細線で囲み、桃色の細点線を入れるとともに、当該行為の内容、面積及び地番を付記すること。 |
(6) 地目未更正箇所等調査
保安林台帳及び土地登記簿並びに国土調査法第17条に基づき作成された簿冊(地籍簿)及び地図(地籍図)との照合等に基づく「経常地籍等異動確認調査」及び「国土調査に伴う地籍等異動確認調査」をもってこれに替えるものとする。
(7) 不在保安林所有者及び当該保安林現況調査
ア 保安林台帳及び土地登記簿等に基づき不在村保安林所有者を把握する。また、その当該保安林の森林機能及び地番境界等の現況について調査するものとする。ただし、当該保安林現況調査については、同条第2号の規定によるものとする。
イ 調査の結果は、団地区分整理表にとりまとめるものとする。
(調査書等の作成)
第7条 調査書、調査位置図及び調査図を、次により作成するものとする。
(1) 調査書は保安林適正管理現況調査書(様式第7号)により整理表、調査表を取りまとめるものとし、2部作成する。
(2) 調査位置図は、国土地理院発行の5万分の1の地形図等により、調査対象地域について、第5条の調査原図の「記載事項1~4」を同「図示の方法」に準じ記入し、2部作成するものとする。なお、調査原図の図面区域及び番号を図示するとともに、図面の余白にタイトル及び凡例を付記する。
(調査とりまとめ等)
第8条 調査とりまとめ等は次によるものとする。
(1) 当該調査の結果、保安林を適正に管理するために改善を要するものについては、早急に措置するとともに、保安林台帳等に調査結果及び改善措置等の履歴を整理し保管する。
(2) 特に、当該調査の結果、保安林境界が明確な地形又は地物界によっていないことが明らかとなった保安林については、現地で保安林境界を見定めた上で、保安林台帳附属図の補助図等を作成し治山地図情報システム等に保管する。
(3) 当該調査の結果、当該保安林の適正な管理のために森林所有者等へ通知する必要がある場合は、通知のうえ適切な指導等を行うものとする。また、保安施設事業等他の事業に協力を要請すべきものについては、当該他の事業との連携を密にして、管理の適正化を図るものとする。
(4) 第7条により作成した調査書等について、町の担当課で保管するものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略